位置・地勢・気候
 すさみ町は、紀伊半島の南南西部に位置し、紀伊山地を背に、白浜町、古座川町、串本町と隣接し、雄大な太平洋に面しています。東西19.25km、南北15.5km、面積は174.45平方kmです。町土の約93%は林野で占められ、平地はわずかです。(H29.10.1 現在)海岸線は豪壮な海岸段丘で、吉野熊野国立公園に指定されています。気候は温暖で、年平均気温は約17℃、年間降水量は約2,300㎜です。
すさみ町は、紀伊半島の南南西部に位置し、紀伊山地を背に、白浜町、古座川町、串本町と隣接し、雄大な太平洋に面しています。東西19.25km、南北15.5km、面積は174.45平方kmです。町土の約93%は林野で占められ、平地はわずかです。(H29.10.1 現在)海岸線は豪壮な海岸段丘で、吉野熊野国立公園に指定されています。気候は温暖で、年平均気温は約17℃、年間降水量は約2,300㎜です。
沿革

すさみ町は、豊かな自然に恵まれ、6世紀代から紀南の拠点であったことが、昭和45年に発掘された上ミ山古墳によって裏付けられています。
平安期には、串本町、古座町、古座川町と共に牟婁郡三前(みさき)郷に属しました。
近世は紀州藩の支配下になり、明暦3年(1657年)周参見に口熊野奉行所(寛政11年(1799年)代官所に改組)が置かれ、東は太田川(那智勝浦 町)から、西は瀬戸鉛山(白浜町)に至る157カ村、石高19,373石の広範な地域を管轄する地方政治の中心地として栄えました。
明治22年の町村制施行により各々藩制時代の村や浦が合併して周参見村、大都河村、佐本村、江住村が誕生し、大正13年に周参見村が町制を施行して周参見町となりました。
昭和30年3月、三舞村大字太間川が分村して周参見町へ編入され、同時に周参見町、佐本村、大都河村の1町2村が合併して、新しく「すさみ町」が発足しました。
その後、昭和31年4月に大字大鎌を江住村へ分町しましたが、昭和34年3月に江住村をすさみ町へ編入合併して、現在に至っています。
すさみ町の合併の経緯
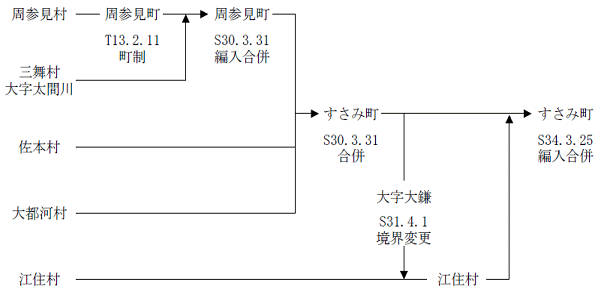
主な産業
 農林漁業と観光を主要産業としています。
農林漁業と観光を主要産業としています。
温暖多雨である気候は蔬菜園芸に適し、戦前からレタス栽培が行われ、良質なすさみレタスは関西随一とされています。
また、海岸段丘を中心にストック、カスミソウ等の花卉栽培も盛んになっています。
漁業は黒潮本流に近い地の利により、明治以来「ケンケン船」の全国屈指の基地として知られ、カツオ、ヨコワ、ブリ等が水揚げされています。
海岸線一帯は関西一の磯釣り・船釣り場として有名です。国指定天然記念物江須崎島、稲積島の原生林等を中心とした豊かな自然美に加えて近年ではマリンスポーツや世界遺産に登録された熊野古道大辺路街道も脚光を浴びています。
町の木・花・鳥・魚
町の木 シイ(スダジイ)

シイは、町内全域に広く分布し、特に県立自然公園内の江須崎島には幹まわり5~8メートルの大木の群生が見られ、貴重な天然樹林となっています。
町の花 ハマユウ(浜木綿)

ハマユウは、ヒガンバナ科の球根類で、夏の間、ひとつの花弁に傘状の花が数十枚開きます。
コルクのような種が海流にのって流れ、温暖な海岸に漂着すると芽を出し繁殖します。
町の鳥 メジロ

あざやかな黄緑色の体をもち、目の周りには白いふちどりがあります。椿などの花の蜜を好み、民家の近くまで近寄ってきます。
町の魚 カツオ(鰹)

南方海洋から北海道までを回遊するカツオは、ケンケン釣り漁の対象としてすさみ町になじみ深い魚です。
すさみ町制40周年を記念し、カツオが町の魚として制定されました。
町章
すさみ町建設の理想である平和、協調、躍進を象徴しています。
全体の形は、「す」の字で、四つ角は合併した4町村(周参見町、佐本村、大都河村、江住村)の協調、円形は平和、すは大鳥が千里の外に向かって躍進せんとする印象強さを表現しています。
 すさみ町章
すさみ町章
すさみ町民憲章 (昭和60年11月制定)
- 豊かな自然を守り、うるおいのある美しいまちをつくりましょう。
- 教養を高め、歴史と伝統にまなび、文化のかおるまちをつくりましょう。
- スポーツにしたしみ、健康で希望にみちた明るいまちをつくりましょう。
- たがいに助けあい、平和で楽しいまちをつくりましょう。
- 働くことを大切にし、活力あふれるまちをつくりましょう。
お問い合わせ
総務課
電話:0739-55-4802
